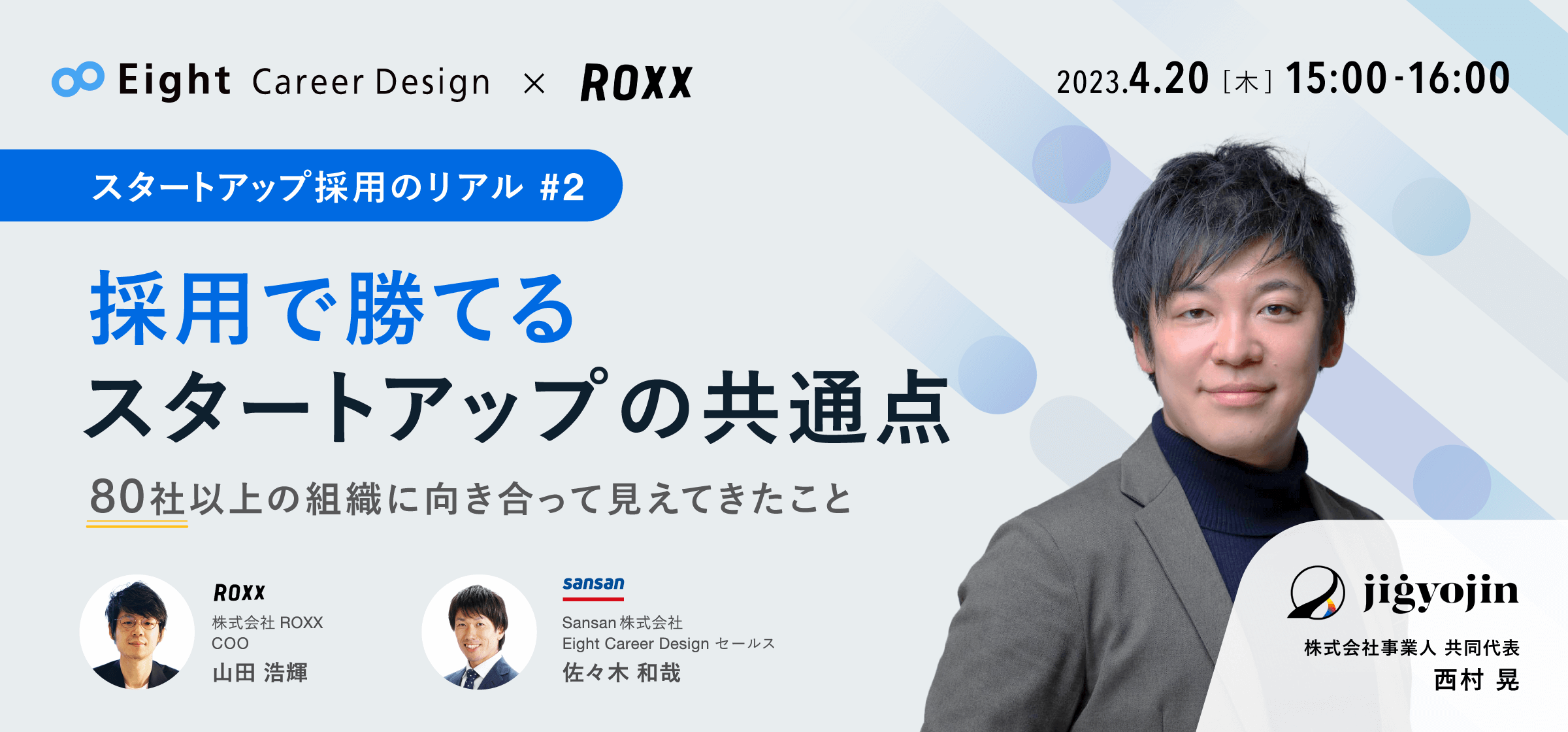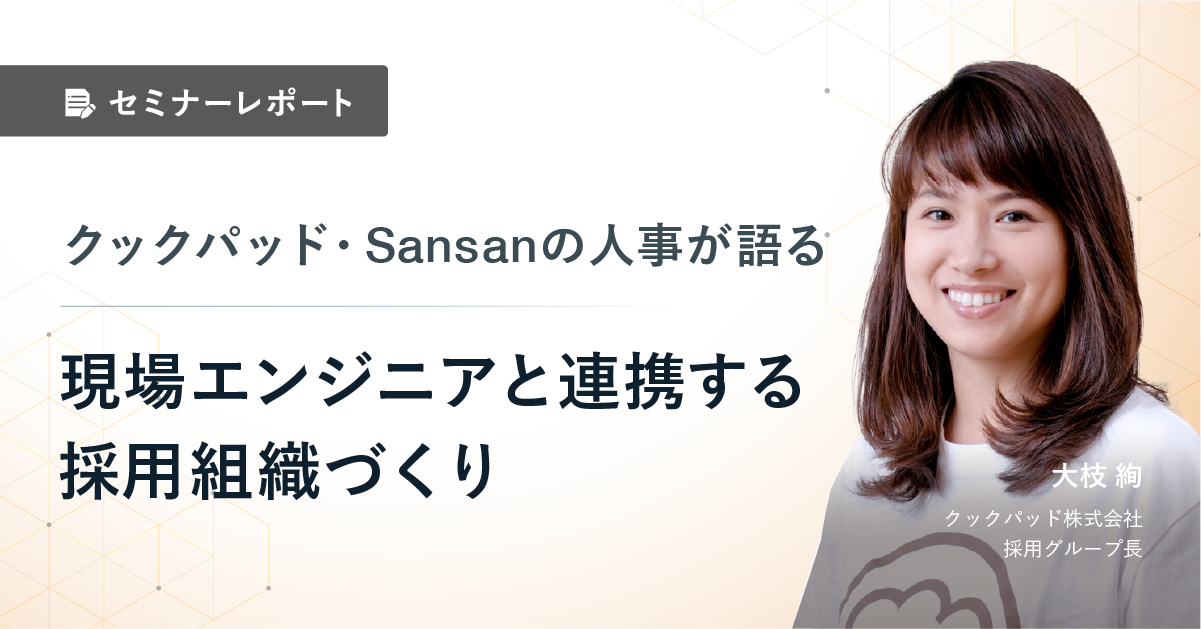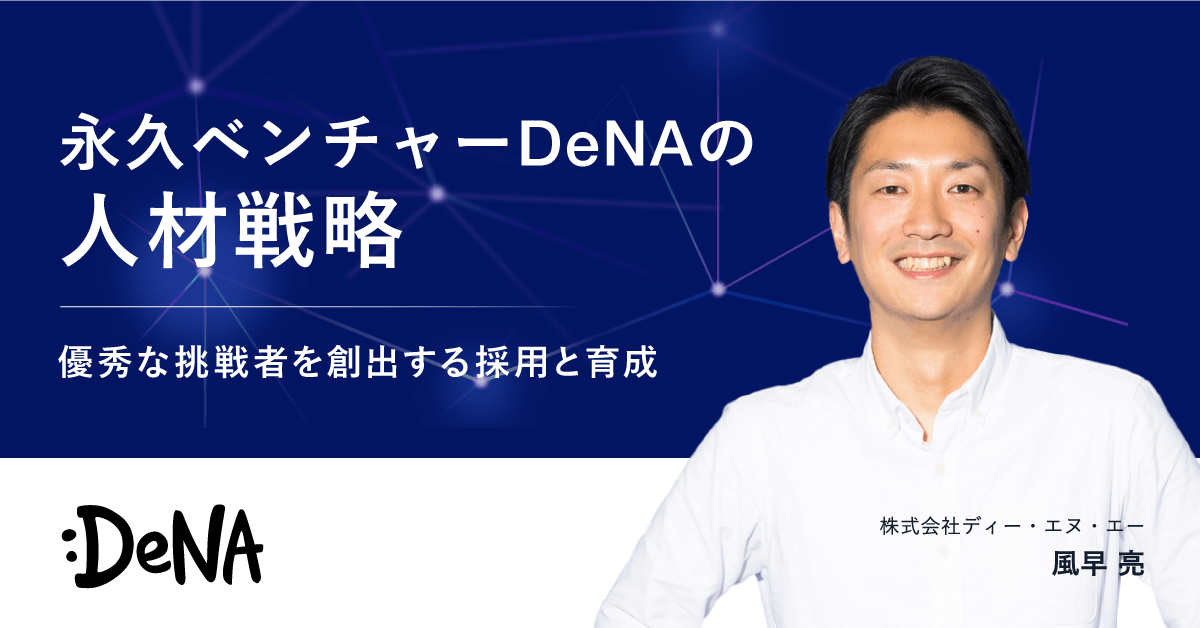2022年11月に政府が発表した「スタートアップ育成5か年計画」では、2027年に年間投資額10兆円を目指すとするなど、近年は新たな事業を興しやすい環境となっています。一方、採用面に関して難しい現状が待ち受けているのはスタートアップも同じだと言えます。
そこで80社以上のスタートアップ企業を支援されてきた株式会社事業人の西村晃共同代表をお招きし、採用のノウハウがなくても強い採用組織を作る施策についてご紹介いただきます。
登壇者紹介

西村 晃(にしむら あきら)
2015年Sansan株式会社の人事部マネージャに就任。2019年株式会社カケハシ入社。、同時に株式会社事業人を創業。2021年株式会社リフカム執行役員社長室長を経て、2022年より事業人の経営に専念。
採用で勝つための3要素①:51対49
西村氏:スタートアップが採用で強くなるため、徹底していただきたい3つのポイント、ひとつ目は「51対49」という考え方です。100対0で競合他社に勝たなくても、転職先としての優先順位を上げて、ギリギリでも上回ることができれば成功だと言えます。
そのために取り組むべき具体的な方法は以下の3点になります。
<51対49のための具体的な取り組み>
1. 自分たちの強みと弱みを明確にする
2. 競合他社との差別化要因を個別の候補者ごとにクリアにする
3. 弱みはドローにして、強みで寄り切る

採用の4Pで自社の強みと弱みを分析しポジションごとに整理
西村氏:強みと弱みを明確にするためには、採用の4Pに沿って自社のそれぞれの魅力や課題を分析しましょう。
<採用の4P >
・Philosophy:理念・目的
・Profession:仕事・事業
・People:人材・風土
・Privilege:特権・待遇

西村氏:自社全体の4Pを分析しつつ、ポジションごとに強みと弱みを洗い出していくと効果的です。ネガティブポイントは伸びしろでもあると理解して、候補者の方に誠実にお伝えしましょう。
またスキルの高い方に対しては「この課題を一緒に解決してほしい」とお話することも大切です。その際に以下のようなシートを活用し、ポジションごとに魅力となるポイントを整理することをお勧めします。

競合他社との差別化要因を個別の候補者ごとにクリアにする
西村氏:さらに候補者別に採用のストーリーを作ることをお勧めします。下記のシートでは右下の「訴求ポイント」が重要です。自社の強みと弱みがどこにあるかを明確にすることにより、例えばスタートアップのフェーズなので5点つけられるが、待遇で他社に勝てない場合は、待遇を論点にせずストーリーメイクしていくと良いでしょう。

西村氏::採用では51対49で勝てれば成功であるというマインドで、弱みをドローに持っていき強みで寄り切って勝つことが大切です。そのために、採用CX(Candidate Experience=候補者体験)を考慮した面接設計をすることで、採用が一段と強くなります。
候補者全員分を作ると担当者に負荷がかかりますので、まずは重要な候補者に対して作成しておくと良いでしょう。

西村氏:採用で勝つために強みと弱みを分析しどのジャーニー(体験)を強化するかを選びながら、自社に合ったストーリーを作っていくと採用の成功率向上につながります。
採用で勝つための3要素②:ヘルプシーキング
西村氏:多くの人事担当者は責任感が強く、がんばり過ぎる傾向があると感じています。そこで大切になるのが「ヘルプシーキング(援助要請)」です。
経営者が採用担当者のヘルプシーキングにきちんと対応できるかどうかは、その後の採用の質にも関わってきますので、トップの方には特に大切にしていただきたいです。
<ヘルプシーキングとは>
Help+Seeking(助け+探し求める):助けが必要なことを自覚して他者に支援を求めること

ヘルプシーキングの4つのプロセス
西村氏:ヘルプシーキングでは告白する勇気が重要です。告白することで大きな課題を乗り越えることができます。
<ヘルプシーキング4つのプロセス>
・問題を認識する:問題を抱えていることを自覚する
・告白する勇気を持つ:自分の問題を告白することはハードルが高いが乗り越える勇気が必要
・サポートを求める:適切な相手とタイミングを見極めてサポートを求める
・サポートを受け入れる:提供されたサポートを素直に受け入れる

採用におけるヘルプシーキング
西村氏:採用担当者にとって、リソース、予算、スキルの3つのポイントでサポートがあると非常に助かります。
リソースが足りない場合は早いタイミングで採用のリソースを追加して欲しいと伝えるべきです。予算では特に採用予算を適切に確保して、予算に応じたオファー年収について、マーケット感覚を伝えながら経営者にジャッジを促したいです。。また多くの工程をこなす中でスキルアップの場を設けることは手が回らないと思いますので、自身のスキルを伸ばすことも大切ですが、外部の力を借りることも重要です。
<採用におけるヘルプシーキング>
・リソース:運用、採用CX(特にクロージング)、人事チームの増強
・予算:採用予算を適正に、オファー年収を適正に
・スキル:スキルアップの場、外部の専門家の力

採用で勝つための3要素③:劣後順位
西村氏:最後にやらないことを明確にする「劣後順位」を明確にリスト化すると、やるべきことの精度が圧倒的に上がります。
中途採用では手法が多岐に渡り、採用担当者は工数過多になりがちです。そこで劣後順位を明確にして、自社の採用フェーズに合わせた手法の選定を行うようにすると効果的です。

西村氏:弊社で1年ほど伴走し現在も継続的に支援している企業では人事担当者の採用において、「人事経験者が欲しい」という要件を劣後させ、未経験でも優秀な方であれば採用することにしました。またエージェントも活用し、事務作業を外注に出すなど、いくつかの工程の内製化を劣後することにより、結果として3名の採用を実現。かなり強い人事体制の構築に成功しました。
<劣後順位の事例>
・一人目人事の採用:人事経験者という要件を劣後させ未経験者を採用
・ダイレクトリクルーティングを劣後させエージェント利用:精度の高い募集要項、効果的な社内フローの構築
・事務作業の内製化を劣後:リソースを候補者コミュニケーションに集中
・二人目人事では「人事のジェネラリスト」の要件を劣後:強いリクルーターを採用し改めて全振り
・超強力な人事部長の採用を1年越しで実現:強い人事体制の構築に成功

アドオンで考えておくべきこと
採用ミスへの対策
西村氏:前に挙げた3つの要素を徹底したとしても、採用ではうまくワークしないケースもあります。採用のミスを減らすためには、自社のバリューをしっかりと明文化して候補者にも選考フローの中で強く理解を求めることや、担当面接官から違和感を訴えられたら、場合によってはその方は採用しない勇気を持つことが大切です。
<採用ミスへの対策>
・バリューは必ず明文化+候補者にも強く理解を求める
・他部署の人でも採用したいと思うか(できるだけ多くの人と接点を持つ)
・面接だけでは見極めきれない:副業や業務委託スタート
・違和感があったら採用しない(人間の勘は案外当たる)

スタートアップが採用に勝つためのマスト条件とは
西村氏:この採用で何を実現したいのか、事業成長フェーズのどのポジションにどんな人材が欲しいかなどをしっかりと言語化している企業は、採用でも非常に強いと感じます。
またリファラル採用は他社とは土俵を変えて闘うという意味で効果的な採用手法と言えます。スタートアップは成長フェーズであり野心的な事業に取り組んでいることを強みにして、投資家の方々や協業先などに有望な人材の紹介をお願いすると良いでしょう。自社のタレントプールを他社とずらしてリファラル採用を推進していくことも成功の秘訣になります。
経営者から採用へのコミットを得るためには
西村氏:現場と経営者との板挟みにお悩みの方に、両者に納得してもらいつつ、特に経営者に採用への理解を深めてもらうための方法をご紹介します。
・人事だけでは解決できない課題(予算など):経営と現場との橋渡し的役割を担う
・現場側に誤りがある場合:経営者と現場責任者に徹底的にディスカッションしてもらう
この場合、ある種のハレーションを起こすことも重要だと思います。それでも解決できない場合は、私たちのような外部の組織に任せてしまうことも大切です。
スクラム採用を促進する要素
西村氏:現場からの協力が大きいスクラム採用には小さな成功体験を短いスパンで積み上げ、ある種のムーブメントにすると協力を得やすくなります。そのために現場側にアンバサダーを作ることが重要です。リファラル採用も同様に、キーマンから採用の重要性を発信してもらいつつ、協力者を増やしていくとスムーズに浸透します。
まとめ
事業成長フェーズのスタートアップでは組織規模に見合うアトラクトの構築や、組織全体として採用の価値観を共有することが重要な施策となります。
またダイレクトリクルーティングやリファラル採用などの手法を、自社の思想や価値観に合った形に落とし込むことで、採用力向上につなげていくことが可能となると分かりました。
革新的な事業の成長と魅力的な組織形成のために、当セミナーのTipsを活かしていただきたいと思います。